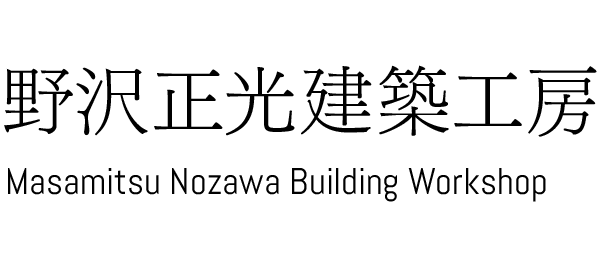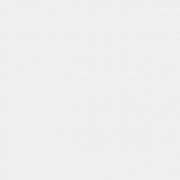山越邦彦のエコロジカルな住宅思想に関する多面的研究 その2
3.山越邦彦のエコロジカルな思想の周辺と相関
山越は住宅設計と並行して,批評や海外建築情報の紹介など,旺盛な言論活動を展開した。本草ではこれらが相互にどのように関連していたのかを明らかにする。
3−1.山越邦彦の近代建築像と「構築」概念の性格
生田勉は,1930年前後に「構築派」を標樗して近代建築運動を実践した「少数」の面々がいたことを示唆している注25)。この「構築派」の急先鋒が,山越邦彦だった。
山越は,1925年に分離派への批判にともない「時はすでに構成派,ネオダダも過ぎ 〈構築派〉 の世に入っている」注26)と説き,1930年には「構築」と把握された近代建築像の確立をめざして月刊誌『建築時潮』の企画,編集,執筆に携わっている注27)。
以下では①分離派との論争,②『建築時潮』の誌面を手がかりに,「構築」概念の性格について考察する。そのうえで③国際的な影響関係について検討したい。
3−1−1.分離派建築会批判における「構築」概念
山田守による東京中央電信局(1925年)は,1920年に設立された分離派建築会の近代建築像を明快に示した建物だが,竣工直後にその意匠が内包する芸術至上性についての議論が生じた。ペンネーム「プルルル生」の朝日新聞鉄箒欄への投稿記事を発端に,①8月7日:プルルル生「中央電信局」②8月12日:M・Y「中央電信局礼賛」③8月16日:プルルル生「建築弁」④9月1日:瀧澤眞弓「工場荘厳」⑤9月9日:プルルル生「再び建築弁」と,分離派同人を巻き込んだ論争が闘わされる注28)。このプルルル生の正体が山越邦彦だった。
中央電信局の意匠を特徴づけるパラボラアーチの造形を芸術至上主義の所産と断じたことから,近代建築の意匠上の要請に対する議論が展開される。山越が山田守と解釈する「M・Y」と瀧澤真弓は,目的としての芸術性を肯定する。だが,一連の議論を通じて山越は,芸術性を追求するためにもたらされるいかなる無駄も批判し,合目的性や客観的妥当性を根拠に「最小労価で最大効果をあげるもの」を目標に据えて,無駄のないところに美
を求める視点,つまり結果として体現される美のあり方の確立を求めている。芸術と把握される伝統的な建築像に転換を迫っているのである。その鍵とされたのが「構築(派)」という概念であった。
3−1−2.『建築時潮』で主張された「構築」概念
「構築」という概念を具体的に喧伝する場となったのが,山越が責任編集の任に当たった『建築時潮』(1930年7月〜31年6月)だった。創刊の辞は次のように書き出されている。「建築の時代は今や過ぎ去らうとして居る。我々は構築時代の暁を体験しつつある」注29)。既成の「建築」は「不合理な計算されない,感覚的な,非物象(ウンザハリヒ)趣味的な,暗い,個人的な,非生物学的,非社会学的な,製図板的建築計画が行われている」ものと捉えられ,その代替として「生物学的,社会学的,健康的,ザッハリッヒカイト,機能的,材料的,構造的,合目的的の研究」に基づいた「構築」という建築像の探求が目指された。個人性,感性,趣味性などに依拠した主観的な芸術としての建築像を,自然科学的・社会科学的合理性,機能性,即物性,合目的性などに根ざした客観的な科学としての建築像へと捉え直すことが企図されていたのである。
3−1−3.「構築」概念の国際的影響関係
山越の提唱する「構築」概念は,1926年に出版された‘‘Der moderne Zweckbau’’でベーネが描き出した近代建築像に近似している。だが山越が「構築」を用い始めた
時期はベーネの書に先んじている。しかし,ドイツ語圏諸国におけるNeues Bauenの動向と併走するものであったことは確認できる。このドイツ語は一般に「新興・建築」と訳されたきたが,山越の場合「新・構築」という訳語を当てている注30)。とくに1923年から26年にドイツで発行された雑誌‘‘G’’でミース・ファン・デル・ローエや,1924年から28年にスイスで発行された雑誌‘‘ABC:Beiyraege zum Bauen’’でスタムが提唱したBauenという近代建築像との顕著な類似を確認できる注31)。山越の「構築」概念は,Bauenという即物的に「建てること」を要請した建築運動と足並みを揃える同時代的な性格をもつものだったといえる。
山越の「構築」概念の性格を考える別個の手がかりが,1929年に実施予定だった講演の「建築→ルート・マイナス1建築→構築」という演題である注32)。建築が構築
に置換される結節点に「√−1(建築)」という数学の虚数の概念が据えられている。当時,虚数の概念を鍵に据えて,科学と芸術を等価におくという図式を提出し,目
標としていた人物にリシツキーがいる注33)。リシツキーは雑誌‘‘G’や‘‘ABC’’でも重要な役目を果たしてる。リシツキーは,機械的な合理論ではなく,自然の生成のシステムがもつ有機的な合理論への着目を示している。作品を哲学や自然認識の体系を再現するものではなく,自然の一部分となることを表現するものとも捉えている。つまりそこには,総体的な環境という観点から全体と部分との相互的連関を充たす有機的な関係が問われており,エコロジカルな発想につながる道筋が内包されてもいる注34)。
3−2.山越邦彦における「成長する家」受容
山越はドーモ・ディナミーカの雑誌掲載に際して「成長する条件を充分に与えて居る」注35)「〈成長する家〉としての条件も考慮した」注36)と記している。それ以上
の記述はないものの,この「成長」という概念が,マルティン・ワグナーが1931年に提唱した「成長する家Wachsende Haus」を念頭に置いたものであることは明白である。それは1930年代前半の日本において,モダニスト建築家の関心を集めた。そして山越は,ワグナーの同名の小冊子の最初の翻訳者であった。
3−2−1.マルティン・ワグナーの「成長する家」
ワグナーが1931年にまとめた小冊子『成長する家』は,1934年から35年にかけて,山越の翻訳で『建築世界』に掲載された。この訳文によって,その理念の全容を知
ることができる。内容は次のとおりである。1:序章,2:需要と供給,3:新しい住居,4:費用と生産,5:技術設備と管理,6:家と庭,7:家屋の拡張,8:形態,9:敷地の調達と開発費,10:都市計画に於ける成長する家,11:成長する家の金融,12:結語。そして最後の第13章として図版が掲載され,付録として先進的建築家による「成長する家」の設計図,説明書,実施建築物の写真24枚が掲載されている。
ワグナーが想定していた生活像は,CIAMの最小限住宅の考えを継承したものであり,生物学的要素として衛生学に基づいた健康的生活が中心的課題として挙げられ
ている。また,女中のいない,それでいて家事労働ができるだけ負担にならない生活,つまり居住者が能率的に家事労働を行える生活が想定され,生活設備面での充実,特に暖房設備に関する考えなども述べられている。
興味深いのは,ワグナーが,具体的な「成長する家」の増築方法として,平屋建てにおける水平方向の増築が望ましいとしている点である。理由は動線経済上の観点と,主眼とする健康的な生活は,何よりも庭という大地との密接な関係において成立すると捉えていたからである。もうひとつ,技術的な理由として,垂直方向に増築することの構造上の不利を挙げているが,ピロティの採用による増築方法については一言も触れられていない。
一方で,材料については,当時の技術的水準を踏まえ,木材およびベニヤなどの木質系材料が適しているとしている。「成長する家」の理念は,1931年にベルリンのバウメッセ主催で開催された「全ての人に太陽と空気と家をsonne luft und haus fur alle」と題する展覧会において具体的に実践された。
3−2−2.日本における「成長する家」受容と山越
「成長する家」は,住宅の設計過程において,あらかじめ増改築を考慮に入れる考えであり,「最小限住宅」を支える考えとして注目されていた。日本において,海外の新建築情報のひとつとして「成長する家」がジャーナリズムにおいて紹介されたのは1932年8月の『新建築』誌上においてである。そこではウィーンで行われた設計競技の応募案5点が紹介されている。また,『国際建築』1933年5月及び7月,8月号においては,ワグナーの小冊子『成長する家』の牧野正巳による抄訳が掲載されている。抄訳ではなく全訳を行なったのが山越で,『建築世界』の1934年3月から35年1月号まで掲載された。
内容的には紹介に留まる記事が多い中,蔵田周忠の「WACHSENDE HAUSについて」注37)は一歩踏み込んだ論考を試みている。蔵田は,日本への紹介記事の多くが,「成長する家」「伸びゆく家」という訳語を用いていることに反対し,「可合成住宅」という訳語を使うべきとしている。それは,計画段階から増築されることを想定した平面計画を行い,最初に建てられる最小限規模の住居と,後から増築される住居部分とが共通した規格による建築部材で建てられる,という認識に基づくものである。
だからこそ,最初に完結した状態で建設された住居に増築される「建て増し住居」(蔵田)と区別するために「可合成住宅」という訳語を提案している。また,蔵田は,「建て増し住宅」が初めから居住者の生活に必要な室を完結した状態で建設しているため,増築部分が僅かな規模となるのに対し,「可合成住宅」では初めの住居は最小限の面積で構成され,増築部は初めの部分とほぼ同じ面積で増築されることが特徴であるとしている。そのことに
より,共通した建築部材の規格統一が適用できると解釈しているのである。
ドイツでの展覧会が開催された1931年には,日本においても市浦健と土浦亀城の自邸において石綿板を木骨架構に貼り付けた乾式組立構法の住宅が実現されている。日本においては,増改築工事の容易さという側面で乾式組立構法が認識されていたが,これらの住宅には,積極的に「成長する家」の考えを採用した形跡はない。1930年から1942年の間の日本において実践されたモダニズム住宅中で,「成長する家」の考えを適用したものとしては,山越邦彦のドーモ・ディナミーカ(1933年),安田清の自邸(1935年),そして福中駒吉のH邸(1937年)と自邸(1938年)の3例のみである注38)。
最も早い事例である山越のドーモ・ディナミーカは,構造は木造で外壁に1尺5寸×3尺を単位とした石綿板を貼り付けた乾式構造の住宅である。居間,食堂,寝室は2階に配され,1階には玄関と書庫のブロック,ボイラー室と浴室のブロックのふたつがあり,その間はピロティとして吹き放しの状態とされていた(図2−1参照)。このスペースが「成長する家」の増築部分として考慮された部分であり,後に,ここには実験室が設けられた(図2−3参照)。山越がピロティ形式を採用したのは,主として,自然対流式床暖房の実験を行うにあたりボイラーを低い位置に設置する必要があったほか,床下部分の湿気対策と衛生設備(浄化槽)設置のためである。
ドーモ・ディナミーカが竣工した1933年は「成長する家」が山越によって完訳される前年である。モダニズムの海外動向として着目し,その翻訳を進めながら,理念の検証と建築的実践とを同時期に試みていたことになる。ドーモ・ディナミーカは,木造乾式構造でピロティという形式を用いて限られた敷地内における「成長」のあり方を示した世界的にも希少な実験住宅であった。
3−3.山越邦彦のドキュメンテーション活動とその理念
ドキュメンテーションは,情報の選択・収集・加工・蓄積・検索・利用という情報管理の理論と方法の体系である。山越はこれに精力的に取り組んだ。情報化社会が訪れる前,コンピュータの普及以前,それは膨大な労力と時間を要する手作業であった。その作業に山越を突き動かしたものは何だったのか。本節では,山越のドキュメンテーションに対する取り組みをたどったうえで,この活動とエコロジカルな思想との関連を検討する。
3−3−1.山越のドキュメンテーションへの取り組み
1960年代前半における山越の回顧注39)に基づいてドキュメンテーション活動を概観する。
1930〜31年に『建築時潮』に連載した海外雑誌記事紹介欄,続く『建築世界』での外国図書の「批評と紹介」欄が,山越のドキュメンテーションの芽生えとなる。文献収集は,海外の著者や出版社に直接寄贈依頼するものだったが,反応は上々で「数年たらずで数千部」が集まったという。その分類整理に悩んでいたときに出会ったのが,「UDCドイツ簡略版」だった。山越のUDC(国際十進分類)に関する学習と探求は,この時に始まる。
戦後1949年より,法政大学教授を務めるかたわら,海外建築情報収集とドキュメンテーションに取り組む。『建築文化』で「建築家の図書室」欄を担当していたとき,資料の中に‘‘Proceedings of the Conference onBuilding Documentation’’を見出す。そこには戦後住宅復興策の一環として。建築技術情報の収集・蓄積・提供のシステムが,建築家たちの国境を越えた協力と各国におけるBuildingCenter設立によって実現しつつあることが報じられていた。山越は日本にもこのような機構が必要と考え,そこで採用されるシステムは世界標準のUDCであるべきとして学習を再開する。
同じ頃,日本建築学会では戦後日本の復興と,そこでの学会の役割が課題であった。そのためには図書館機能の充実が必須と,学会図書委員の武藤清は山越に図書委
員を委嘱,職員に原田(所)正七を採用して態勢を整えた。図書委員会はさっそく分類法の審議に入り,山越はUDCの有効性を説明して「UDC英国簡略版」の採用
が決まった注40)。この時期,山越は設立されたばかりのUDC協会(1958年に日本ドクメンテーション協会,86年より情報科学技術協会)でも建築部門を担当している。
1951年,日本建築学会はUDCによる図書整理と同時に,内外雑誌から採録した題目にUDC標数を付して『建築雑誌』巻末「文献目録」に掲載,会員からの文献請求に対応するサービスを開始。これにより,かつて山越が期待した日本版BuildingCenterが実現したといえよう。
1952年には日本学術会議国際十進分類委員会委員にも就任している。
1958年に科学技術庁所管で設立された日本科学技術情報センターは,科学技術振興の一環として欧米の約3,000誌から主要記事を抄録,これをUDCで分類・速報する事業を開始した。その建築領域については日本建築学会が協力することになり,もっばら山越が担当した。
山越が日本建築学会を拠点として推進したUDCによるドキュメンテーションの効用は次第に認められるところとなり,大学の建築学科図書館や大手建設会社研究所などでも採用されていった。こうした山越の活動に対して,1971年,「建築分野における情報管理一国際十進分類法の普及一」という功績により日本科学技術情報センター丹羽賞が贈られている。
3−3−2.山越におけるドキュメンテーションと生態系の論理
山越のドキュメンテーションに対する尽力はもっぱら基盤整備に向けられたようにみえる。しかし,彼がドキュメンテーションに期待していたのは,当然のことながらその効用であった。山越は,システムの構築者ではなく利用者でいたかったはずである。ただ,先駆者の常として,自分が使いたいものは自分でつくるしかなかった。1920年代半ばに始まる山越のドキュメンテーション活動は,その連続だったように思われる。
ドキュメンテーションの効用について,山越は講演注41)で,次のようなエピソードを紹介している。
山越は戦後,独自の浄化槽に続いて厨芥処理槽を考案し「溶芥槽」と名付けた。自然界に存在するバクテリアの分解作用を利用して厨芥を土に戻すシステムである。ある時,これを導入した施主からクレームがつく。残飯が腐らない,キャベツの葉が1カ月も青いままだ,という。考案者の信用に関わるので原因究明にかかると,厨芥と一緒に台所洗剤が溶芥槽に流れ込んでいることがわかった。洗剤の主成分である界面活性剤ABS(アルキル・
ベンゼン・スルフォン酸)が,バクテリアの分解作用を妨げていることが原因と思われた。
そこで,これまでに蓄積していたドキュメンテーション・カードでABSを検索すると,ヨーロッパやアメリカで発表されたABSによる水質汚染に関する論文が多数見つかった。海外ではすでに規制に動いているという。反面,国内論文は1本もない。それどころか,当時の日本は中性洗剤の急速な普及期で,河川の水が泡立つなどの異常が話題になり始めていた。山越は,これを放置するとABSが井戸水や水道水までをも汚染すると危惧し,一刻も早い問題提起を考えた。
こうして新聞に掲載されたのが,山越の記名記事「処置のない汚水」注42)である。ここで山越は,ABSによる環境汚染を告発し,中性洗剤対策を訴えた。この行動の動機を「水の問題は直接には私の研究範囲ではないが,国民全体の衛生の上から,世界的には純粋なわが国土の水の質をまもる上からも,緊急な重大事と感じて」注43)と述べる。それは,かつて1930年代に実験住宅を設計したときの,生物工学=生態学に基礎を置いた理念,す
なわち「技術によつて生命を損耗することではなく,技術形態を生活体に奉仕するやう生活態の多様性に適応せしむることによつて生命を獲得する」の実践であった。
そもそもは小さな溶芥槽の中で起こっている現象の解明から始まったことであり,とりあえずは施主と自分の問題であった。しかし調べてみると,それは地球環境と人類全体の問題につながっていた。山越は蓄積された科学技術情報の網目をたどって,そこにたどり着いたのである。その導き手こそがドキュメンテーションであった。ドキュメンテーションによって構築される世界は,山越にとって,情報空間に再現された生態系にほかならない。