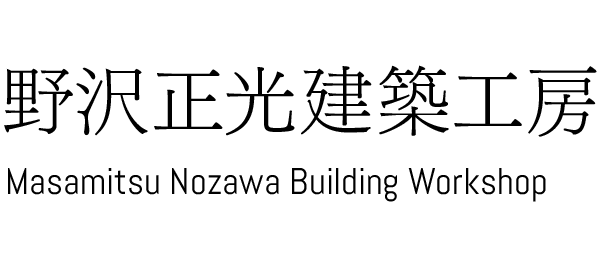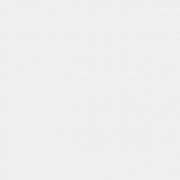清家さんについて (住宅建築2007年1月号)
学生のころ、友人と坂道を登りながら清家さんの家を探し探し見つけだして覗き込んだことをそのはじめとして、かなり以前から清家さんの初期の住宅のいくつかを見ている。「森博士の家」「斉藤助教授の家」「宮城音哉邸」「秋山さんの家」それからいうまでもない「私の家」「続私の家」などだ。そしてそれらのいくつかについては、数度にわたって訪れる機会を持っている。特に真鍋弘氏が「建築知識」編集長であったころ数度にわたり取材を兼ねて清家さんにお目にかかり話を聞きながら濃密に訪れた「私の家」を懐かしく思い出す。
何より清家さんの戦後すぐに始まるいくつもの小住宅のほとんどはこの国の住宅に珍しく今日まで現存し健在である。過去、何度か訪れることができ、うまく行けば今日でもまた赴くことが可能なのは何よりそれが今日そこにあることによっている。清家さんの住宅の多くはクライアントの意思で壊されることがない住宅であったのではないか。なぜそうだったのだろうか、一般に規模の小さな戦後すぐの住宅の多くは生活の姿が変わる中でその寿命を終えていった。そのなかで彼の住宅は偶然、まれに、運良く、愛され使い続けられている。もちろんこれに尽きるのだろう。抑えられたヒューマンなプロポーション、モダンなデザイン、これだけでは清家さんの意図を類推しながら手繰り寄せ納得できる説明にしたということにはなるまい。たしかに清家さんが今日生きていたとしても彼は笑いながら「運がいい」としか言わないだろうとも思うのだが。
若き清家さんはこれ等住宅の発表の折にもっと丁寧にそれらについての説明を試みている。以前取材の折、そうした記事を僕なりに読み直したことがある。「架構と舗設」それはその中で見つけた、なるほどと思わせるキーワードであった。清家さんの設計の家はこれらの分離が極めて顕著である。最近残念ながら解体されたと聞くがあの宮城音哉邸では家具、間仕切りなど「舗設」(清家さんの言う「ほせつ」とは「設え」=「しつらえ」のことだろうとおもう、この稿では「設え」とさせていただく)のほぼすべてを渡辺力に委ねてさえいる。「架構」を「設え」と意識的に分離する、これにより自在な室内が家族の生活の経過する時間なか、当然起こりうるさまざまな模様替えの要求にこたえることを可能とし、それが住まいの陳腐化をもたらすことなく、長く使われ続ける。これが第一の理由なのではないかと思う。
「架構と舗設」は今の言葉で言えば正確に「サポートとインフィル」こうなるはずである。オープンビルディングシステム、架構と舗設を分離する。私がこれをオランダのハブラーケン等の構想であり、社会住宅設計建設の主要なツールであると知るのはわたしが 20代の後半のころであり、大学同期の才媛、中澤富士子氏による詳細な紹介記事が特集された「都市住宅」1972年9月号の中であった。仮にハブラーケン等のこうした思考が戦後すぐのヨーロッパに既にあったと考えても清家さんの思索はいかにも早いと言えるのではないか。
清家さんが海軍機関学校の教官であったころ、たくさんの格納庫を設計したと聞いたことがある。「架構と舗設」はそれをルーツにするのかもしれないと思うことも可能だ。格納庫はサポートだけがある建築だろう。どう考えても格納庫に作り付けの家具や間仕切り、つまり「設え」はありえない。
そして、もうひとつ50年代の清家さんの設計する住宅に設備されるパネルヒーティングについてである。自宅のそれは特によく知られている。彼はそのころから「温熱」のための装備を必須のことと考えているように見える。戦後の最貧の時代、小住宅の室内気候をサポートし快適な室内気候をもたらす床暖房を必須とする建築家はほかにそうは見当たらない。ぼくはそれを彼の住宅が長く使い続けられたもう一つの根拠ではないかと思う。建築が作り出す気候である。これも実は格納庫につながるのかもしれないのだ。格納庫には戦闘機がいつでも飛び立つことができるよう暖房があったとの話も清家さんから聞いたものように記憶する。ただ、清家さんの話はどこか幾分怪しいにおいとニヤッとしたくなるユーモアをはらむものであった。どこまで本当であるか、私に確たる証拠があるわけではないが。
奥村昭雄、この人も私のより近い先達である。奥村さんとは20年を超える昔「ソーラー研」と称しああだこうだと議論をしながらパッシブソーラーシステムを考えた。この人が戦時中、舞鶴の海軍機関学校で清家さんの教えを受けたと知ったときはそのめぐり合わせに驚いた。不思議なつながりである。しかも建築のフィジックス、特に温熱を興味の中心としているところが似てもいる。そう考えると僕はいつの間にかこの二人の思索に親近なものを僕自身がもっていたことに気づく。考え試みるフィールドが重なっている、と気づくことになる。「住宅は骨と皮とマシンからできている」という本はこの辺を頼りに書いたものだと思う。骨と皮とはスケルトンであり架構である。そしてマシンとは気候コントロールのための装置のことである。
時代が思索を開く。この二人は私の周辺にさまざまな形で存在する人々のひとりひとりであり、思索のひとつひとつであった。それは書籍でも映像でもないじかに応答することのできる、等身大の身体であったのだと思う。私はたまたまそれに遭遇した。そしてそれが私の主要な部分を作ったのだろうとおもう。
ここで私自身の自宅を見よう。まずは「架構」=サポートを。高さのない、がらんどうの架構である。鉄骨である。コンクリートブロックの壁がある。ハブマイヤートラスがある、床下に太陽熱を空気で送るシステムがある、既製品がまれにしか存在しない。さまざまな思索のモンタージュをここに見ることが可能だ。清家さんがいる。奥村もいる。吉村、イームズ、上遠野徹さんがいるのだ。「設え」=インフィルを見よう。それらは「架構」と明確に分離され手いる。設計に伴って計画された間仕切り家具などの多く、外部の庇などにいたるまでどれも取り外し可能である。ちなみに集められた椅子は奥村さんの手になるもののほか多くは清家さんの家にもあるモーエンセン、ウエグナーなどデンマークのものだ。
清家さんに教えられながら思う。「架構」を構想し「気候」をデザインする、この二つを解くこと、「使い続ける住宅」に求められる課題は突き詰めるとこういうことになるのではないか。住宅の中に改めて「架構」を構想することは「設え」をそれから意図的に分離することになる。それは「設え」の短期での変更、改変を可能とし「架構」の100年を超える存在を可能とするのではないか。そして「架構」の中に作り出すべき「室内気候」は人々の快適な生存のための環境として必須となるのではないか。
そしてそれは最小の資源使用量によって、住まいが慎重に作られ、飽きられることなく長く生活を快適に包み、結果として改修されながら長期維持されること、「サステイナブルデザイン」につながるのではないか、と考えるのである。
清家さんの家は見事にそれに対応するものと思う。この二つが明確に意図されることのない建築がその対極にある。
「気候」、過去、伝統建築はわれわれの住む日本が比較的温暖であると考えること、無意識の「我慢」によって「気候」に対峙することの無い建築であることを特徴とするものであったのかもしれない。「気候」は建築によって作られるのではなくコタツ、火鉢または衣服により局所的に作られるものであった。もちろんその時代、今日の「快適」はイメージとしても存しない。
「設え」、伝統木造住宅において軸組みが「設え」そのものとまったく重なっている事に気づく。伝統木造住宅は間仕切りつまり設えが直接大地に露出し、屋根がかけられたもの、と捉えることができるのではないか。横架材までの厳密さに比べ小屋組みが自在でどうにでもなるいいかげんなものであるのもそのせいかもしれない。住宅寿命が今日に至るまで「設え」の変更のスケジュールに似たものであることも必定であったと考えることもできるのではないか。我慢が普通であった長い間、人々はそうしたささやかな「すまい=設え」を維持し生活を営んできたのだろう。初期のコンクリート造公団住宅の中にはまさに木造住宅が正確に設えられていたことを思い出す。
家とは、人々にとり、それは生まれる以前からすでにあるものである。家を構想するときすでにあるそれが大きな起点となることはごく当たり前のことだ。我慢ができなくなる中、露出する「設え」を暖房するのである。このことがいかに無益で非効率でとんでもない非効率な営為であることかが気づきにくい。「サポート」「架構」とは熱的性能をも含むシェルターのことである。そしてそれなしに今日的意味での建築が存在しにくいことを意図的に理解し確認しないまま長きにわたり「設え」にさまざまに意匠が凝らし、それを建築的営為と考える、室内気候をまったく射程にしないものであったと考えることができるのではないか。
説得力ある過去の根拠、論理を鑑賞しその上に冷静な思考をめぐらせる、独創とは実はそうしたものなのではないか、と強引であることを多少覚悟で思うのだ。建築は技術であり、気候であり、科学である。そしてそれは最小の資源により快適を求めるさまざまな科学、工学と同衾するもののはずである。建築は構築(バウエン)であってほしい。グロピウスが清家さんに見たものはまさにそれであり、それによる共感であったと思う。またバウハウスの思索は吉村に清家にそして奥村に通底するものであったと考えて不思議は無い。あの時代の建築が比較的ささやかであること、そして大きい開口部と低い天井を持つことが、ヒーティングのため、ダイレクトゲインのためであったと考えることをたのしみとすべきであり、それが結果新しいプロポーション、新しい「美」を生んだのだと理解すべきなのであろう。そこからは新しくそれから連続し成果を挙げる思索が生まれることになったはずである。いまさらいうまでも無いが師と仰ぎ結果としての造形に無思考に憧れ、絶対の「美」にそれを押し上げる、いわば伝統の芸の宗家と弟子のような固定、それからは新しい思索は生まれるべくも無い。清家さんに学ぶ楽しさを思いながら、考えることの充実を思う。