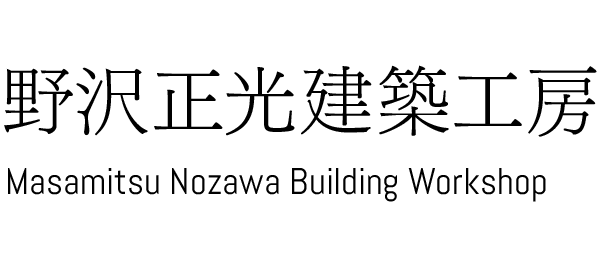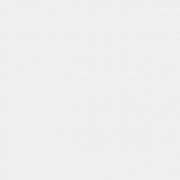都市への手がかりを建築に求めて 前川國男と都市
【松隈】今回は、「前川國男と都市」というテーマをかかげました。前川國男は都市をテーマにした建築家ではない、と一般的にはいわれています。しかし、前川は、最終的には、一つの建築の中に都市的なものをいかにしたら織り込めるか、に設計作業を集中させていったのであり、やはり都市は大事なテーマだったのだと思います。「輝く都市」を構想したル・コルビュジエに学んだ前川國男は都市をどう考えたのか。今、都市の問題はいろいろな意味で混乱しており、切実に解決策を見つけなければならない難しい時代です。前川がテーマとした都市とは何か、そして、現代の都市をどうするのか、を考えてみたいのです。
今日、お招きした野沢正光さんは、大高正人さんに学ばれました。大高さんは、前川の下で、「神奈川県立図書館・音楽堂」や「東京文化会館」を担当し、独立後は「多摩ニュータウン」など、都市をテーマにしてきた建築家です。野沢さんは、大高事務所では、広島の「基町高層アパート」を担当し、世田谷区の宮之坂駅のコンペでは一等を取り、集合住宅や駅という視点から都市のことを考えてこられました。
もう十年以上も前のことですが、一九九二年に、「神奈川県立図書館・音楽堂」の取り壊し問題が起きました。そのとき、野沢さんは保存運動の中心になって活動された。それは音楽堂が残る大きな力でした。その経緯を、私は後ろからずっと見ていました。
また、その少し後の一九九七年に、前川が都市居住をテーマに設計した「晴海高層アパート」が、再開発で姿を消しました。情けないことに、跡地は駐車場になっています。そのときも、野沢さんが建物の大切さを訴えていました。そうした前川建築との関係からも、野沢さんに、「都市」をキーワードに話していただきたいと思います。
【野沢】野沢です。松隈さんから、「前川國男と都市」について話してほしいと依頼されたとき、「テーマが重たすぎて、無理だよ」と言ったんです(笑)。そうは言っても、都市は幅も広いし、都市と建築は切っても切れない関係ですから、このテーマを脇に置きながら、前川さんのことを考えてみるのも良い機会かもしれない、と思って出てきました。
■前川國男との出会い
私が忘れがたく覚えている前川さんの姿があります。それは、「国立西洋美術館新館」の緑色タイルの増築ができた直ぐ後、友人と出かけた折、中庭をはさんでル・コルビュジエの本館と向かい合う休憩コーナーがあったのですが、そこに、前川さんがひとり立っておられたのです。びっくりしました。でも、そのとき、前川さんは、自分が設計した建物ができた後に、どのようにそれがひとびとに使われているかをこっそりご自身でで確かめに来るような建築家だと思ったんです。とても印象的な光景でした。
以前、『GA』というガラスメーカーの質の高い社外報が「前川國男とテクニカル・アプローチ」という特集を組んだことがあります(一九九六年秋号)。このとき、内田祥哉さんにインタビューして、「前川さんをどう見ていましたか」とお聞きしたところ、「戦後の焼野原の時代に本建築を作れる建築家は前川さんだけだった。他の建築家は仮設的な木造建築しかできなかったのに、前川さんだけが鉄筋コンクリートの建物を手がけていて、うらやましかった」と言われた。
前川國男は、戦後すぐに、期待される建築家として大きな任務が肩にのしかかることになったのだと思います。一九五四年に音楽堂を作ります。このような建物を、まだ誰も作っていない時期に、作ることを前川事務所は期待されたということです。そういう意味で、前川さんは、悲劇の人ではなくて、もっとも恵まれた建築家だったと思います。
■技術を通して建築を考える
ところで、私は大学卒業後、大高事務所に入ったのですが、当然ながら、設計の実務を担当する中で、自分で考えなければならないことがたくさん出てくるわけです。そのとき参考にしたのが、建築の雑誌と実物の建物だった。そうした中で、当時出版されていた、『建築』という正統派建築雑誌に、前川事務所の田中誠さんの、「建築素材論?テクニカルアプローチとデザインの接点を求めて」という連載がありました(一九六一年八月号〜六二年六月号)。そこには、プレキャスト・コンクリート、窯業製品、スティール・サッシュなど、いわば前川建築を成り立たせている三大ツールとでもいうべきものが具体的に紹介されていて、建築をどのように考えて、どのように作ったかが、きちんと報告されていました。
私は、もともと技術的な工夫が際立っている建築が好きな方だったので、田中誠さんの記述のていねいさと、建築へのアプローチの姿勢に感激したのです。そして、こういうことを考えることが建築を作っていくことなのだ、と教えられました。建築の形は、突然に表われるようなものではなくて、一つ一つ、たとえば工法とか、生産合理性とか、そのようなものの積み重ねからできている、テクニカル・アプローチというのは、おそらくそのことを意味していたのでしょう。それが、僕にとってとてもなじみの良いものだったのだろうと思います。
その後、前川さんの仕事に、書き手として触れる機会がありました。「原点としての設計スピリッツ」を特集した『建築知識』の三〇〇号記念号(一九八三年七月号)です。一九五〇年代の建物をとりあげて、みんなで書き分けたのですが、私が担当したのは、前川さんの「日本相互銀行亀戸支店」でした。ほとんど誰も知らない建物です。私は子供の頃祖母の家に行く折に、プレキャスト・コンクリートの南京下見板の外壁をもつ、この建物の横を通っていました。戦後の街中に、白い建物がぽつんと立っていた。私の近代建築初体験のひとつが、この「日本相互銀行亀戸支店」なのです。もう一つは、修学旅行で鎌倉に行ったときに見た、「神奈川県立近代美術館」です。建物に光が反射して真っ白に輝いて見えました。
■都市を経験する
「神奈川県立図書館・音楽堂」は坂倉さんの「神奈川県立近代美術館」同様当事の知事、内山岩太郎の発案で戦後いち早く作られた前川さんの初期の傑作です。しかし、さきほど紹介がありましたが、その建物がバブル期の再開発計画によって取り壊される、という不穏な噂が伝わりました。それで、「それは困るよ」と、保存を訴える声を建築家や音楽家が上げ、私もその動きに加わったのです。そのとき、なぜこの建物が壊されると困るのか、を考えざるを得なかった。そこに建てられた経緯や都市の中の建築のありようを、建物が壊されるかもしれないという切迫した状況の中で、新たに知り、確認することがたくさんありました。そのときから、私は、「都市」を経験することになった、ともいえます。
その保存運動の最中に、「音楽堂が危ない」と、担当者だった大高さんに伝えに行ったところ、大高さんは、設計したころのことを懐かしそうに話してくれました。現在は、江戸東京たてもの園に移築された「前川國男自邸」で音楽堂の図面を描いたそうです。ご存知のように、前川事務所は戦争で事務所を焼失し、戦後の活動は前川さんの自宅でスタートしたんですね。それで、板の間の居間に製図台を並べていた。夏はあまりに暑いので、上半身裸で描いていると、前川さんが帰ってくる。帰ってくると裸では怒られるので、慌ててシャツを着たそうです(笑)。そんな状況で音楽堂は設計されていた。
「そのとき、設計の参考にしたのが、ロンドンのテムズ川の河畔に建つ「ロイヤル・フェスティバル・ホール」の報告書だった。そこには、こうすれば、経験的ではなく、きちんと科学的に音響がデザインできる方法が詳細に書かれていた。」、と彼は話しました。もちろん、当時は、前川事務所も、音楽ホールを設計した経験などありませんから、必死になってその報告書を読んで設計したのです。「あれがなかったらできなかった」と言っていました。
そうなると、私も、ロンドンに行った際は、フェスティバル・ホールに行かないわけにはいかなくなってしまう(笑)。でも、毎回そこへ立ち寄るようになって、都市と建築についていろんなことを学ぶことができたと思っています。それは、音楽堂や日本の公共建築と、フェスティバル・ホールが置かれている状況の違いです。
■ロイヤル・フェスティバル・ホールの教え
フェスティバル・ホールのホールの下、ホワイエは、いつ行っても公開され、音楽会が行われています。無料です。人があふれ、ビールを飲んで楽しんでいる。本屋もCDショップも開いている。バーもあって、スナックスタンドもあります。時間をつぶしながら快適でタダでいられる場所が、維持、管理、運営されているのです。街の公共施設はこうやっていつも市民に向け開いているものなんだ、ということを教わりました。
二〇〇一年に、フェスティバル・ホールは、開館五〇周年を迎えましたが、ロビーには、『五〇年目の大改修』というパンフレットが置いてありました。内容は、今後一〇〇年使うための増強案の詳細な説明と、そのための募金の呼びかけでした。「みなさん当事者でしょ、楽しくここで遊んでいるのだから、少しは出してよね」という調子です(笑)。いくつかの仕掛けが、サービスと対価の緩やかな要求として、盛り込まれているんですね。横には今度使う椅子の実物まで置いてある。大改修が終わるのは二年くらい先ですよ。でも、すでに椅子は決まっていて、「今度、君たちこれに座れるんだぜ」という感じなのです。
そのパンフレットを見ると、担当する建築家だけでなく、それを支える技術コンサルタントまで、十チーム以上の名前が記されていたと思います。オーブ・アラップのような有名な構造コンサルタントの他にも、防火は誰がやる、積算は誰、などと書かれています。パンフレットを見て、寄付しようという気にさせるような、楽しげな仕掛けになっている。大高さんは、「音楽堂は、フェスティバル・ホールを参考にした」と懐かしそうに言いました。私は実際のロイヤルフェスティバルホールを見て、都市の公共施設は本来こういうものなんだと思ったのです。日本に帰って、神奈川県立音楽堂に行くと、コンサートのない時は、扉がぴったり閉まっていて、暗黒の空間といいますか、ホワイエも寒々しい。私たちの街は、ロンドンがもっている都市のサービスを欠いていることに改めて愕然としたわけです。
■近代建築をわかりやすく語ること
さて、音楽堂を壊そうとする不穏な動きがあったとき、私たちは、単純に「困るじゃないか」という思いで保存運動をはじめました。しかし、実際に動き出してみると、「保存を訴えるには音楽堂でシンポジウムをやるしかない。でも難しい」と、みんな弱気になっていた。その打合せに、私がたまたま遅れて行って、「できる、できる!」と言ったのでやることになったと、後で聞きました。(笑)こうして、音楽家と市民、神奈川県立音楽堂を利用しているたくさんの人たちが熱心に動いてくれて、シンポジウムが見事にできたのです。
その中に、「浜の会」という名前だったと思いますが、横浜市内をボランティアで案内するグループの人たちもいました。彼らに、「街をガイドする際に、例えば、港の見える丘公園に建っている古い洋館は説明できるけれど、音楽堂のような近代建築は説明の対象から外れている」と言われたのです。それを聞いて、これは私たち建築の世界にいるものの怠慢だと思いました。私たちは、音楽堂は、近代建築として問答無用に良いのだと思い込んでいたわけです。でも、今まで普通の人にわかりやすい言葉で説明することを怠ってきたのではないか。「近代建築の良さを説明してください」と言われて、私たちは、急遽、近代建築の説明をするトレーニングをさせられた。それは、私にとってもうひとつの大切な経験でした。
やはり、街は、専門家がこうしたらどうだろう、こうしたらわかってもらえる、こんな手間のかかったサービスなら良い反応を示してくれるだろう、といった仕掛けがあって、はじめて楽しむことのできる場所になるのだろうと思います。ロイヤル・フェスティバル・ホールのスタッフたちが日々画策しているようなことですね。私たちがいかに市民に説明できるのか。それは、建築がポピュラーになってつまらなくなったり、反対に高尚なものになっていくのとは違う。建築の楽しみ方をきちんと説明できること、偉い人がやっているので黙っていなさい、ということではなくて、建物を作るときもできたときも、きちっと市民と応答することが、楽しい街を作っていくことにつながるのではないかと考えるのです。
■一九五〇年代の近代建築とレプリカ
そういう意味では、前川さんの日本相互銀行本店や神奈川県立図書館・音楽堂、坂倉さんの神奈川県立近代美術館など、一九五〇年代の建物は、私たちにとって大切な文化財のはずです。これら全部を残したとしてもたいした数ではないでしょう。今の私たちを取り巻く変化の中では、こうしたものは明日なくなってもおかしくない状況です。その一方で、コンドルの設計した「三菱一号館」が突然、レプリカとして戻ってくる。「それは本物といえるのか」という感じもあって、建物の保存とは何か、そして、都市の風景をどう継承していくのか、が大きく問われています。このことは、私たちの後の世代にとっても大問題です。わたしは街に空虚感を作ってしまう、街自体が捏造された一種の書き割りになってしまう危険性を感じるのです。
■前川建築をたどる
ここで、私の前川建築体験について少しだけ紹介します。私は、もちろん前川さんの建物を全部は見ていません。でも、あまり期待しないで行って、本気でびっくりし、感激したのは、「岡山県庁舎」です。これはすごいと思いました。このカーテン・ウォールにはあきれました。本当にへなへなのサッシュ・バー。サッシュ・バーは、鉄を押し出して作る小さなL型や十型をしたものです。そのサッシュ・バーにパテでガラスを止めるスティール・サッシが当時ありました。それをカーテン・ウォールに全面的に使って、腰パネルは、ベコベコを防ぐために亀甲型にプレスして、立体的な形にしたスティール板で組み立てられている。このファサードに陽が当たって、不思議な光り方、金色に光る。たいへん驚きました。この建築はその後も数次にわたり前川事務所によって丁寧な増築改修が行われていて前川建築の変遷を知ることもでき、サステイナブルな建築使用の好例でもあると思います。『前川國男作品集』(美術出版社,一九九〇年)の中でも扱いは大きくないですが、一九五〇年代の傑作です。
次に、一九六一年にできた「東京文化会館」です。神奈川県立図書館・音楽堂とは十年も時間的な隔たりはないのです。そこには、この建物にかけられたエネルギーと、自在にデザインできるようになった能力、そして、もう一つ、十年ほどしか経たないうちにできたという、当時の日本の経済的成長をも表しているのでは、との気がします。
私が東京芸術大学に通っている頃には、すでに「東京文化会館」は建っていまして、毎日のようにこの前を通り、中に入って二階の精養軒でチャプスイを食べたりしました。芸大の音楽学校のつてで、建物の裏から入ってタダで音楽会を聞くこともしました(笑)。そういう意味で親しみのある建物です。
もうひとつ、「東京海上火災本社ビル」です。この建物のように、前川さんの建築には、公開された広場が必ずどこかにありますね。前川さんのウルバニズム(都市計画)では、都市の中に建築を作る、建築の中に都市を作るという方法が試みられていくわけです。
今は、この建物も、丸の内に無数にある超高層ビルの一つになって埋もれたようになっています。しかし、建設された当時は、皇居のそばに高い建物を建てるのはまかりならぬ、という美観論争が起き、前川さんは、広場を作り出すために一人孤軍奮闘しなければならなかった。そういう意味では、都市というのは厄介なものです。
■ウルバ二ズムへの距離感
ところで、一九五五年、「国立西洋美術館」の設計を依頼されたル・コルビュジエが、はじめて日本にやってきます。その頃の日本は、まだ、焦土の風景を色濃く残していたのだと思います。僕にはおぼろげな記憶しかないのですが、今から考えますと夜になると真っ暗になるような都市でした。そのとき、コルビュジエは、自分の下で学んだ日本の三人の建築家、前川國男、坂倉準三、吉阪隆正に向かって、「君たちは、これからウルバニズムを担うことを覚悟しなさい。この状況で街を考えなくてどうするのだ。今なら、まだ白紙ではないか」と言ったそうです。コルビュジエは建築と同じように都市への提案を描いた人ですから、よくわかる話です。また、彼が言うことに説得力のある状況が日本にはあったのだと思います。
しかし、前川さんは、都市全体の計画ではなく、一つの建築を作ることと格闘しなければならないという役割を引き受けようとしたのだと思います。一つ一つ建築材料を選んだり、サッシュや打込みタイル、プレキャスト・コンクリートを開発する。当時の日本は、そこから始めないと近代建築ができない、という状況にあったからです。近代建築をスタートラインにつけるという宿命を引き受けようとしたに違いない。そうなると、ウルバニズムまでとても手が出せないというのが、前川さんの本音だったと思います。
これは、東京文化会館の模型です。当時、東京都が用意した「国立西洋美術館」の敷地と「東京文化会館」の敷地を、画然と分けている敷地主義みたいなものがありました。そのままでは、建売住宅のように、決められた敷地にぽつんぽつんと建ってしまう。これでは、アーバン・デザインとはいえないと、前川さんも担当の大高さんも考えて、上野公園と東京文化会館と国立西洋美術館の敷地境界を無視して、原理的に計画を立てようとしたわけです。建物の大きさは変わらないから、どこに空地ができてどこに建物を建つかの関係が変わるだけですから、役所の所有権を一度バラせば、公園と建物があいまって、良いかたちのオープン・スペースができるのでは、と提案したときの模型です。
しかし、役所は、当然ながら、「余計なことはしなくてもいい、敷地の中に建てろ」と言ってくるわけです。そうしたやり取りを何度か粘り強く繰り返したものの、最後は、役所の仕組みを突き破ることができなくなってしまう。それでも、そういうことをきちんと議論して、より良い街、より良い都市環境をどうしたら作れるか、をまじめに提案している。ともかく原理的に考えている。場合によってはゼロから考えることを可能な限りやってみる。前川さんとスタッフは、当時、そこまでやろうとしていた。すごいなと思います。
状況は変わって、今では、前川さんの展覧会も開かれますし、吉村順三さんの展覧会も開催される。レーモンドの展覧会も予定されているそうです。私たちの先輩の建築家たちが、何をバトンタッチしながら現在に至っているか、を考えるのに、今年、二〇〇五年はとても良い年です。それを考えることは、自分たちが建築家としてやっていく上で大きな励ましにもなる。建築を考えること、そして、建築を手がかりにして都市や市民や社会に視野を広げることは、逆に建築を考えることに戻ってきます。そう考えると、あの時代に、前川さんが果たしたことは孤高であり、エリートの仕事だったと思います。
■市民と応答する建築へ
少し乱暴な言い方ではありますが、前川さんの時代には、提案する市民、当事者としての市民は存在しなかったので、建築家は役所との奮闘になった、と言えるのではないでしょうか。これからはその辺が変わってくる。市民との応答で建築を作っていくときに、建築家が自分のサービスできる建築の「品質」を自覚的に考えていくことは、ますます大事になってくると思います。その一方で、建築に対する社会の期待が大きくなってきて、建築の存在感が社会の中で増してくると、建築がフローになって経済に巻き込まれてしまう危険もある。オーソドックスで、きちんとした建築を作ることが、私たちにできるのか。テクノロジーは本当に人々を幸せにできるのか。求められる社会環境に対して、建築は何が用意できるのか。それらの問いに答えようとする作業を、前川さんは、一人でやっていたという感じがします。頼るものは自分の中にだけある。そういう意味では、自分の立場に責任をもって、孤高に見えるほど頑張った建築家です。私たちは、周りに豊富な情報がある分だけ、自らの頭で考えることをしないでいるのではないでしょうか。