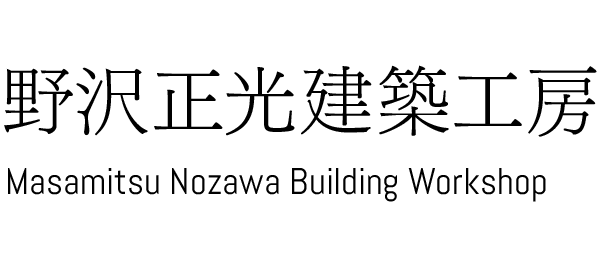日本におけるサスティナブル・デザインの可能性 「10+1」Vol.48
これからは私の作品《長池ネイチャーセンター》(ニ〇〇一)です。日本でのサステイナブル・デザインの可能性というと僕はひとつは木造にあると思います。僕は稲山正弘という構造家と木造の建物をいくつかやっています。彼は、木構造をめり込みとか変形を計算し解析します。日本の木造というもの持続可能性のすごさを僕らはなんとか追究できないかと考えています。今まで筋交、壁でしか解析できなかったものが、めり込み計算などによりさまざまな解析できるようになり木造の考え方そのものが変わりつつあると考えています。昔の技術、伝統技術をそのままやるのではなくて、そうした伝統技術をも巻き込みながら、明日何ができるかというのを考えてみたいと思っているのです。
《いわむらかずお絵本の丘美術館》(一九九八)これも僕の設計した建物です。これもめり込みを計算を根拠にした構造計算をしているんですが、こうした架構は大工が非常に飲み込みがいい。そういうことで大工の頭の中にある合理と僕らがここでやっていることはとてもうまくつながっているという確信がこのときはありました。つまり大工は僕らが提案していることをすごく喜んでいるはずで、大工たちが長い間考えていた合理の延長線上に発展するかたちがありうるということを彼らは理解したのではないかと考えています。ここでは地元の樹齢八○年ぐらいの杉材で作っています。そうすると、二酸化炭素の発生量はとても少ないです。アメリカ産材料を持ってくるとか北欧産材料を持ってくるとかウッドマイレージといいますが、輸送にかかる二酸化炭素発生量がありますから。先ほどの話とつなげると「意図的な貧しさ」というのは皮肉にも金がかかります。プレカットや外材は、貨幣で比較すると驚くほど廉価です。大工を使い、地元の木材を使うことはとても金のかかることとなってしまっています。しかし、大工のテクノロジーの伝承は存亡の危機に来ているものの、それをうまく活かすことができれば間違いなく日本独特の新しい木造ができる。大工の総合的な腕力、合理的な思考回路みたいなもの、それを使える国は日本だけですね。しかも新しい貨幣/負の貨幣とでもいいましょうか、二酸化炭素をコストとして計ればこのほうが圧倒的に合理的でもあるのです。
最後に「デュラブル(DURABLE)とサステイナブル(SUSTAINABLE9)についてちょっと触れたいと考えます。福田晴虔さんの著作にある話の受け売りです。デュラブルというのはジュラルミンのもとになった、永久不滅であるという単語です。サステイナブルとは相当違う概念です。つまりサステイナブルは、ちょっと言い過ぎかも知れませんがふらふらでよたよたなもの、ずっとペンキを塗りつづけないと腐っちゃうようなものを使い続けるという持続です。要は「貧しいもの」の「意図的」な持続です。本当にそんなものがあるかどうかは別として、黙っていても持続していくもの、そうした永久不変なものがサステイナブル・ソサエティ、サステイナブル・デザインの求めるものではなく、手を入れたり直したり支えたり、場合によってはもう一度考え直したりしながらずっとサステインしていくもの、そういうあり方こそサステイナブル・ソサエティなのだいうということです。考えてみればあたりまえですね。その一見面倒くさそうな宿題を面白そうに解く。その楽しさはサイエンス/技術がここニ〇〇年にわたり楽しんできたものでもある。われわれの宿題もその延長のなかで楽しみと独創を秘めている。サステイナブルな思考はそうした思考そのものと考えていいのではないか。社会はそうした思考、独創にきっと共感と拍手をしてくれるはずで、その辺はポジティヴに思っていいと思います。
▼質疑応答
難波和彦──僕はこれまでに野沢さんの話を断片的には聞いていましたが、まとめて聞いたのは今回が初めてで、ようやく全体がつながった気がします。みなさんは野沢さんのフットワークの軽さに翻弄されたかもしれないけれど、あちこち細かな話題を散りばめながら、最後には全体でサステイナブルというテーマに収斂していくという、とてもわかりやすい話で、僕は感動しました。
松村秀一──野沢さんとブルネルの組み合わせはまったく意外でした。ブルネルという
のはなんか僕のなかでは大立て者ですよね。もうちょっと違う話をされるのかなと思っ
ていたので非常に面白くお聞きしました。たぶん、野沢さんがおっしゃっているサステイナビリティとは、結局は社会全体の考え方ですよね。個々の人がどうこうという問題ではなくて、社会全体の受け止め方とか仕組みの問題とか。僕はなかなか楽観的に考えられないタイプなのですが、明るい未来を感じさせるものがあるという確信を持っていらっしゃる。そういう僕のために例えばこういうところに出てるよというのがあれば教えていただきたい。
野沢──一番影響を受けたのは、例のレイナー・バンハムの「環境としての建築(The
Architecture of the Welltempered Environment)」(鹿島出版会、1981)です。あれは必読書です。原著が出版されたのは一九六九年ですから、三五年以上も前の本ですね。新しいものですと、齋藤晃「蒸気機関車の興亡」(NTT出版/一九九六年)とか「蒸気機関車の挑戦」(NTT出版/一九九八年)、杉浦昭典『蒸気船の世紀』(NTT出版/一九九九年)和辻春樹『随筆──船』、(NTT出版/一九九六年)などを思い出します。技術屋さんのモチベーションというのはみんな善意なんですよね。橋が落ちちゃったりしますから後で反省したりするんですが。技術屋がストイックになったってしょうがないだろうと思います。
難波──ブルネルの話で僕がひとつ印象深く覚えているエピソードがあります。松村さんが言うように、当時の彼は王立建築家協会の重鎮で、一八五一年のロンドン万国博覧会の企画者でもあったので、立場上、会場の最初の案を設計しました。しかしこれが工期も費用も無視した重厚な案で、結局若い温室技術者のジョセフ・パクストンの《クリスタルパレス》をつくったわけで、それが結果的にどういう空間になるのか、まったく予想もしていなかったと思います。できたあとに、自分のやったことの凄さに自分で驚いてしまう。それを自覚し次のプロジェクトに意図的に適用しようとした途端、どこかにブレーキかかかるというか、同じパターンをくり返すことになってしまうのではないかと思うのです.ブルネルもそうだったし、パクストンもそうだった。
今日の野沢さんの話に通底しているのは、やはり技術の重要性ですね。ブルネルやパク
ストンのようなエンジニアたちか生み出してきた技術が巨大化して、近代文明、近代文化
近代建築が生まれた。それが肥大化して今や地球環境を壊しているわけだけど、だから技術を捨てましょうということでは絶対に解決できない。むしろ技術をもっと繊細に、もっと細やかに、もっと高性能にコントロールしていかなくてはいけない。そこでかつてのブルネルたちが考えたような知恵が、もう一度必要とされている。鉄骨造そのものは確かにサステイナブルじゃないイメージがあるけれど、それを支えてきた技術や人間の知恵は、−九世紀以来洗練され蓄積されているので、それを否定してはいけない。そういう意味で、今日の野沢さんの話は鉄骨の話題から始まったと理解すると、とても話が通りやすいのではないでしょうか。
野沢──そのとおりですね。あと僕が建築の勉強をして良かったと思うのは、建築には歴史の先生がいらっしゃるということです。
難波──東大工学部の図書館問題というのがあって、工学部のなかで図書館をすべて統括してしまおうという話あります。そういう動きに、建築学科だけが反対してる。なぜかというと、ほかの学科は純粋にエンジニアリングだけで、歴史なんかに興味はないのです。エンジニアは最新の技術にしか興味がない。しかし建築は文化的な側面が重要で、新しさだけが価値ではない。
野沢──ミュンヘンのドイツ博物館に行かれるといいですよ。大英博物館のように植民地から持って来たものはあまりない。だけどドイツ博物館には汽車、飛行機、鉄橋の模型や、ダムや河川管理の土木技術の書籍などがなんでこんなに並べるんだというくらいあります。そうした振り返る方法というの持っていない、過去になにを考えたのか分からないということは困るよね。
難波──僕の考えでは、そういうカルチュラルな面、歴史的な面があることが、その学問の成熟度を示していると思うんですが、工学部のなかでそういうことを主張しているのは建築学科だけです。
野沢──土木学会が出版した日本中の土木的ヘリテージを、登呂遺跡から始まって近代までずっと並べたすごくきれいな本があります。旅行に行くときに持っていくといい本です。建築であれランドスケープとか風景とか、文化財とかいろんなことを考えるのは僕たちの仕事に入っていると思います。あれは日本の土木系の歴史が作った見事な成果だったと思います。だから歴史を体系化していこうという動きはほかの分野でも始まってはいる。