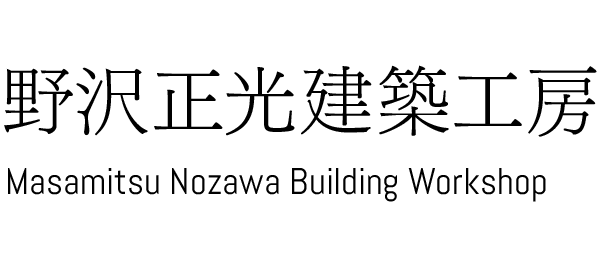全日本海員組合本部会館の改修
東京都港区

©SOBAJIMA, Toshihiro
建設地:東京都港区
改修竣工:2024年12月
構造:RC造 ※既存
階数:地下3階,地上6階 ※既存
敷地面積:990.85㎡ (299.73坪)※既存
建築面積:449.44m2(135.95坪)※既存
延床面積:4135.00m2(1250.83坪)※既存
用途:事務所
設計:野沢正光建築工房
構造:山辺構造設計事務所
設備:ZO設計室
家具:Koizumi Studio
サイン:水野図案室
展示室・図書室企画:梅ノ木文化計畫
施工:竹中工務店
掲載誌:新建築 2025年3月号

©SOBAJIMA. Toshihiro

©SOBAJIMA. Toshihiro

©SOBAJIMA. Toshihiro

©SOBAJIMA. Toshihiro

©SOBAJIMA. Toshihiro

©SOBAJIMA. Toshihiro

©SOBAJIMA. Toshihiro

©SOBAJIMA. Toshihiro

©SOBAJIMA. Toshihiro

©SOBAJIMA. Toshihiro

©SOBAJIMA. Toshihiro

©SOBAJIMA. Toshihiro

©SOBAJIMA. Toshihiro

©SOBAJIMA. Toshihiro

©SOBAJIMA. Toshihiro

©SOBAJIMA. Toshihiro

©SOBAJIMA. Toshihiro

©SOBAJIMA. Toshihiro

©SOBAJIMA. Toshihiro

©SOBAJIMA. Toshihiro

©SOBAJIMA. Toshihiro

©SOBAJIMA. Toshihiro

©SOBAJIMA. Toshihiro

©SOBAJIMA. Toshihiro

©SOBAJIMA. Toshihiro

©SOBAJIMA. Toshihiro
*
*
*
改修前

©SOBAJIMA. Toshihiro

©SOBAJIMA. Toshihiro

©SOBAJIMA. Toshihiro


©SOBAJIMA. Toshihiro
大髙正人による設計の1964年竣工のオフィスビルの改修。組織本部の拠点として、当初は建替が検討されていた。大髙に関する書籍や展覧会に関連したシンポジウムの企画等の文化活動の影響を受けて、所有者の本建物と建築文化への理解が深まったこともあり、建替ではなく改修をすることとなった。改修では建物を今日的性能に引き上げるための更新と、歴史と原設計を尊重し文化的価値を継承するための保存・復元を両立して達成することが求められた。
青木繁による原設計の構造計画は、大架構(2つのコアとそのベース、コアを上下で繋ぐ大梁)と、小架構(各階の梁せいと荷重を極力小さくするジョイストスラブとその端部固定のための独立柱)の、大小2つの架構の組み合わせとなっている。これにより地上階の主な内部空間には柱壁がない空間が実現されていた。原構造設計は地震荷重を1.25倍としていたこと、8階建ての計画であったが6階建てで建設されていたことにより、耐震改修は増築部の減築と片持ち部の上下振動を抑える支柱の設置のみの軽微なものとすることができた。本改修ではスケルトンにして全箇所の既存躯体検査と、不具合箇所には補修を行っている。
プレキャストコンクリートによる庇・手摺と、奥まったところにある細いサッシによる特徴的な外観を保存しつつ外皮性能の確保を図って、特注スチールサッシと真空断熱ガラスによる外部建具と、室内木製建具によりダブルスキンを形成した。ダブルスキンは空調のレタンルートを兼ねて、レタンエアが外部負荷を吸収することでペリメーターゾーンの温熱環境を向上させている。レタンルートのダクトレス化により、現しが可能となったジョイストスラブ間を半開放のダクトと見立てて、空調空気の搬送路として活用している。
改修で不要室を廃止しプランの効率化を図り、地下の空いたスペースの代わりに、新設となる公開エリアとしての展示室と図書資料室を計画した。地下大会議室は従来から存在した段床を段数を増やしてゆるやかにし、サイトラインの確保された座席スペースを拡大した。音響性能を確認するとともに必要設備を付加して、講演会や演奏会、上映会等、多用途に活用できるよう既存意匠を保存・復元しながら機能的に改修している。増築部の解体により原設計にあったサンクンガーデンを復活させた。サンクンガーデンには外部から直接アクセスできる外階段を新規で計画し、1階と地下公開エリアの公共性を高めている。サンクンガーデンとロビーの間は大きく開け放つことができる木製建具を採用し一体的な利用も可能にしている。
改修におけるそれぞれの所作は既存の部分と新規の部分が対比を保ちながら対話関係におかれるように工夫し、既存要素と改修要素を合わせてひとつの建築としての全体性の獲得を目指している。生きている建築をさらに磨きをかけるように品質・機能・文化の価値の向上を図る改修を試みた。(T.S)